|
|
春菊は日本の料理などにもよく使われる野菜で、特徴のある風味がある葉物野菜です。
栽培が比較的簡単にできるので、家庭菜園やプランター栽培も盛んにおこなわれています。
春菊栽培で気をつける必要のある病気の一つとして、べと病が知られています。
べと病の原因はカビ菌で、初期症状としては、黄色の斑点が発生しますが、その後葉の裏のすす状のカビが発生し、黒色に変化していきます。
べと病が発生すると、春菊の株自体が枯れてしまうことがあるほか、他の株にもうつっていくので、早めの対策が必要です。
春菊のべと病に効果のある農薬や、べと病対策、べと病の予防法について解説していきます。
春菊のべと病に効く農薬とは?
春菊のべと病に効果が期待できる農薬の一つとして、Zボルドー水和剤をご紹介します。
【Zボルドー水和剤】
|
|
Zボルドー水和剤は、塩基性硫酸銅を有効成分としている農薬で、殺菌作用により、べと病の原因であるカビ菌に作用しべと病の予防効果が期待できます。
水に希釈して散布することで、春菊の葉の表面に、膜を作り、少しずつ放出される銅イオンによって殺菌効果を発揮します。
カビ菌などの糸状菌の他に、細菌にも効果があるので、幅広い病気の予防をすることができます。
治療効果についてはあまり期待できないので、べと病の発症前に使用することをおすすめします。
散布後の降雨の量にも依存しますが、概ね2週間から3週間の間効果が持続するので効果的に使用することが可能です。
春菊の他、大根やハクサイなどのアブラナ科、ナスやトマト、ジャガイモなどのナス科、エンドウなどのマメ科、玉ねぎなどのユリ科の野菜に適用できるほか、果樹や花卉にも対応しています。
べと病のほか、白さび病、軟腐病、さび病など多くの病気の予防効果があることが確認されています。
日本農林規格(JAS)の有機農作物栽培に関しても、使用することが認められています。
使うにあたっては、取扱説明書を確認し、必要な保護具等を使用することをおすすめします。
ベト病対策とは?
春菊がべと病にかかってしまった時のべと病対策について解説していきます。
春菊がべと病にかかっていることを確認したら、べと病になっている葉を取り除くようにしましょう。
そのままにしておくと、べと病は他の葉に伝染していき、春菊の株全体に広がっていきます。
取り除いた葉は、ビニール袋などに入れて捨てるようにしましょう。
畑の隅や、プランターの近くなどに置いておくと、べと病が広がってしまう恐れがあります。
葉を取り除く際には、べと病の葉だけではなく、周囲の葉も思いきって取り除くようにしましょう。
発症はしていなくても、べと病の原因であるカビ菌が、くっついていることがあり、後になってべと病を発症してしまうことがあるからです。
べと病が一つの株の中で広い範囲で広がっている場合には、株ごと抜き取ってもよいでしょう。
べと病の株を残しておくと、周囲の春菊の株にべと病が広がりやすくなるので気をつけましょう。
べと病などのカビ菌を原因とする病気は、地面に近い方から発症することが多いのが特徴です。
カビ菌が土の中に潜んでおり、雨などによって舞い上がって、春菊の葉につくことがあるからです。
べと病の早期発見のためには、春菊の株の下の方や、春菊の葉の裏などをよく確認するようにしましょう。
春菊のべと病を予防するには?
春菊にべと病が発生しないようにするための予防方法について解説していきます。
参考にしてみてください。
べと病はカビ菌を原因とする、湿気が多い環境に長い間さらされることで発症しやすくなります。
春菊を育てる際は、水はけの良い場所を選択して、育てるようにすると良いでしょう。
水はけが悪い場合には、土壌改良を行うか、高畝などにし、春菊の株の周囲に、水気が長い間停滞しないようにしましょう。
湿気が春菊の周囲に停滞しないようにするために、風が抜けるような工夫も必要です。
春菊の畑は、風が良く通る場所に作るようにしましょう。
プランター栽培の場合も、風通しの良い場所にプランターを置くことをおすすめします。
春菊は株間を十分に確保して定植や播種を行うようにしましょう。
密植を行うと、べと病の発生が多くなることがあります。
べと病のカビ菌は、降雨時の土の跳ね返りなどで、春菊の葉につくことがあります。
春菊栽培の際は、マルチングなどを行うと、降雨時の土の跳ね返りを抑え、べと病の発生を低減することができます。
春菊に限らず、連作を行うと、さまざまな病気や害虫が発生しやすくなることが知られています。
連作をさけ、春菊以外の野菜を植えていく輪作を行うことで、病気や害虫を抑えることができます。
まとめ
1.春菊のべと病に効く農薬やベト病対策と予防法は?
春菊のべと病に効果のある農薬や、べと病対策、べと病の予防法について解説していきます。
2. 春菊のべと病に効く農薬とは?
Zボルドー水和剤は、塩基性硫酸銅を有効成分とする農薬で、べと病の原因であるカビ菌に作用し、予防します。
カビ菌などの他に細菌にも効果があるので、幅広い病気の予防に効果を期待できます。
春菊の他、アブラナ科、ナス科、マメ科、ユリ科などの野菜にも対応しています。
3. ベト病対策とは?
春菊がべと病にかかってしまった際の対策としては、まずべと病の葉を取り除きましょう。
べと病の葉の他、周囲の葉を取り除くことで、べと病が広がるのを抑えることができます。
べと病が広がっている場合には、株ごと抜き取るようにすると良いでしょう。
4.春菊のべと病を予防するには?
春菊のべと病を予防するには、水はけを良くすること、高畝、風通しを良くする、株間を保つこと、マルチングの使用、輪作を行うこと、などがあげられます。
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37fe82c5.75ec4316.37fe82c6.b4453218/?me_id=1396011&item_id=10002381&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreenaid%2Fcabinet%2Fp3_0420%2F0443_01_p3.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

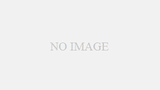

コメント